待ちに待った、週末がやって来た!
まずは、パッケージを開けてみる、アンテナの構成はU字型のアンテナ部と、長さ約3mのコード、コードの先はミニプラグとシュガーライターソケットとなっていた。
 |
|
アンテナをパッケージから出してみる…
|
まずは、アンテナ部だが、先端のキャップを外すと「スパイラル」形状のアンテナが入っていた。
つまりバネ状のアンテナがキャップの中に隠れていたのである。
電波という物は面白いもので、理論的に言えば、電波の波長1/2の長さのアンテナであれば一番感度がいいのだが…
ここで、高校で習った電波について、おさらいを……
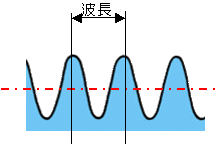 |
|
う〜ん・・これが電波の概念だ!
|
電波は波と考えて下さい。
波の、ある高さから波打って、また同じ高さにまで戻ってくるまでの間を「波長(はちょう)」と言います。
この「波長」が1秒間に何回あるか、言い換えれば、一秒間の波の数を「周波数」と呼んでいます。
例えば、一秒間に波が10回あれば、「10Hz(ヘルツ)」となります。
次ぎに単位ですが、電波は、振動数が多いので、1000Hz(ヘルツ)は1kHz(キロヘルツ)、1000kHz(キロヘルツ)は1MHz(メガヘルツ)で表します。
それと、周波数と波長の間には必ず次の式になるという法則があります。
周波数(MHzメガヘルツ)×波長(mメートル)=300
ゆえに
波長(mメートル)=300/周波数(MHzメガヘルツ)
次ぎにアンテナの概念だが
アンテナの全長が波長の半分(半波長という)のとき、一番電波を強く発射したり受信できます。
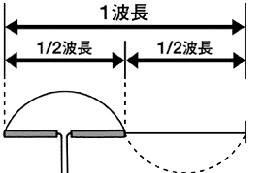 |
|
あ〜ん・・これがアンテナの概念だ!
|
ところが、まともに半波長(1/2波長)の長さにアンテナを作ると、それでもメートル単位の長さになってしまいます。
そこで半波長の半分、1/4波長でアンテナを作るのです。
それでも長過ぎる時は…
さらに、その半分、また半分と、どんどん効率が悪くなってしまいます。
ここで電波の不思議なんですが、1/2波長や1/4波長の長さのアンテナを、バネの様にして短くしても感度は変わらない…という法則があります。
マルハマのAGS-175 は、そんな電波の性質をうまく利用して作られており、さらにU字型の下部には増幅器(ブースター)がビルトインされていたのです。
早速、現在のアンテナを外し、いよいよAGS-175を取り付けてみます。
今回はフロントガラスに取り付けるので、意外と取り付け部には苦労しました。以前、お話しましたが、背の高い系のクルマであれば、ガラス面積が大きいので取り付け場所には苦労しないのですが、セダンでは必然的にリヤガラスかフロントにしか取り付ける事ができません。
う〜ん…高性能ながら(まだ結果は分からないが)あまり市場で受け入れなかったのは、実は取り付け部が制限されたから?などと考えてしまった。
実際に取り付けし、モニターでチェックすると…
以前取り付けていた、同じマルハマのアンテナとは比べるべくも無いくらいに鮮明に写るではないか!
厳密に比較する為に、リヤのパルウスをキャンセルして、モニターチェックしたが、ほとんど画像の鮮明さの低下は見られない。
これは、噂とおりにすごいアンテナかもしれない…。
実際に走行してみて、やはり単体では山陰やビルの陰では、マルハマだけ、またはパルウスだけでは画像の鮮明さが失われてしまう。
さらに、パルウスでは感じなかったのだが、このマルハマでは取り付ける高さによって受信感度が変わってくるのだ。
通常は、できるだけ高い位置へ高い位置へと設置したくなるものだが、こいつは意外と高い位置より、低い位置の方が受信感度が良いのだ。
ところが、低い位置に取り付けると目障りになってくるのだ、まあ考えてみるとセダンでこいつをフロントに付けようなんていう人は皆無かもしれないが、取り付けの自由度という事からは、なかなか制限を受けてしまう…というのが事実であった。
やはり、設置場所の自由度から、これからの主流は、パルウスの様なプリントタイプなんだろうと…
最終的には、フロントグラスのほぼ中央、ルームミラーの近くに取り付ける事となった。
フィーダータイプの二股タイプから、色々なタイプの室内アンテナが登場したが、いよいよ、ひとつの形が完成しようとしている。
高性能と機能性の融合が図られて、室内アンテナの「新たなる旅立ち」が始まった。




